
12年前の記事再読。英語教育が愚民化教育にならぬよう「読み書き中心」で文法を重視し、古典・物語を取り上げていきたい!
1)「戦後に英語教育を読み書き中心にしたのはGHQ。それで日本人は英語が話せない」という説の真偽は不明
今日(2011.02.23)は新英研メーリングリストで以下のようなやりとりがあった。
●新英研メーリングリストへのOさんの投稿
本日19時から始まった読売テレビの番組「鶴瓶の超ゆる~い会議」の中の「なぜ我々は英語ダメ」というトピックの議論を見てましたところ、その結論として、デーブ・スペクター氏の持論である「GHQ陰謀説」が正解とされていました。それは、GHQが日本人の漢字識字率を調査したところ、極めて優れているということが分かり、
「こんなに識字率が高い日本人に英語を学ばせたら、すぐに覚えてしまって、また自信をつけてしまう」と恐れ、そうならないように英語教育を読み書き中心にしたという説です。
2)ルターは「読み書き中心で文法と古典を取り上げていきたい」
●Oさんの投稿に対するルターの意見
この番組の送るメッセージが「かつての読み書き中心主義がダメ」で「オーラル中心の語学教育が良い」というふうになっていることが私は気になります。
① GHQの陰謀が失敗し、良い結果をもたらしてしまうこともある
この番組での言説自体が意図的(陰謀的!)になされていると思います。
「読み書き中心の英語教育はGHQの陰謀だった」ので「読み書き中心はダメ」という結論が導かれ、それが今後のオーラル中心の語学教育を促進する根拠になっており、番組を観ている人々は「やっぱり英語ではオーラル中心の語学教育が大事だ」と思うはずです。
ここで立ち止まって考えてみましょう。「GHQの陰謀だった」からダメとはならないのではないでしょうか? GHQの陰謀説自体が怪しいですが、仮にGHQの陰謀だとしても予想していなかった良い結果をもたらしてしまうこともあるでしょう?
3S政策(さんエスせいさく)とは、
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
screen(スクリーン=映像鑑賞)、
sport(スポーツ=プロスポーツ観戦)、
sex(セックス=性欲)を用いて
大衆の関心を政治に向けさせないようにする愚民政策とされている。
3S政策で日本を愚民にするために野球を持ち込んだら、イチローさんや大谷翔平さんのような名選手が誕生してしまうとか!
愚民にするためにハリウッド映画を持ち込んだら、『サウンド・オブ・ミュージック』『チャップリンの独裁者』を観て、平和を愛する日本人が増えてしまったとか!(私のことです…)
同じように「読み書き中心の英語教育」にしたら、教科書でO・ヘンリー『最後の一葉』『賢者の贈り物』、ジョージ・エリオット『サイラス・マーナー』、テニスン『イノック・アーデン』を中高校生が読んで心が陶冶され、英語教育を通じて日本の民度や霊性が向上して愚民化に失敗してしまったとか。以上挙げた4つの物語、英語教員のみなさんご存じですか! こういった物語を英語の授業に取り戻していこうではありませんか。
②「読み書き中心」「文法重視」「古典・物語」で学び、教養を身につける
よく考えてみましょう。本当に「読み書き中心はダメ」なのでしょうか? かつて、サイドリーダーで『英米名詩選』『英米名文選』でバートランドラッセル『幸福論』などのエッセーを都立高校で学んでいた時代もありますし、有名私立高校ではオーウェル『動物農場』を読んだりしていました。その頃の学生の方が読み書きの訓練をした結果、明らかに英語読解能力、文法力、語彙力、和訳する日本語力が高かったと思います。
③日本の英語学習者は「読み書き:話す聞く=7:3」で良く、英語の授業では文化(culture)と態度(attitude)を教える
話す機会が圧倒的に少ない日本の英語学習者は「読み書き:話す聞く=7:3」で良いとルターは考えます。英語の授業では文化(culture)と態度(attitude)を教える必要があると思っています。
文化(culture)とは、宗教、文学、詩歌など
言葉の持つ文化や背景を教えなければ、その言語が理解できたとは言えませんから、キリスト教、ギリシャ・ローマ神話、シェイクスピア、ことわざ、詩歌(poetry)、マザーグース、ライム(rhyme)、修辞学(レトリック)は必須でしょう。
マニュアルのようなゴミみたいな説明文から情報を読み取って、教養がつきますか? 人格の陶冶ができますか? 無理でしょう!
この話は、漢文に置き換えてみればわかりますね。
なにもつけていない白文は読めない。中国語としては話せない。でも、書き下し文を読むことで意味がわかる。五言絶句や七言絶句が押韻することも知識として知っている。杜甫や李白の作った詩を鑑賞する。故事成語を覚える。その結果、教養が身につく。
現在の指導要領は高校現場から漢文、古文をなくし、この伝統的な教育を廃そうとしているわけですね。
マニュアルのようなゴミみたいな説明文から情報を読み取って、教養がつきますか? 人格の陶冶ができますか? 無理でしょう!(大事なことなので2度目です)
態度(attitude)① 対人の態度
態度(attitude)とは、文字通りの「対人の態度」もあります。
●わからないときに、日本的な態度で黙ってしまうのではなく、Pardon?のように問い返す。
●相手が話しているときは、相づち表現を挟んだり、アイコンタクトをとる。
態度(attitude)②スピーチレベルを考慮した発話
それだけではなく、以下のような「スピーチレベルを考慮した発話をすること」も態度(attitude)に含みます。
●I want「ほしい」だと子どもの発言で不躾なので、I’d like「好ましい」を使う。
●Can I have this one?「これ、もらっていい?」だと子どもの発言で不躾なので、
Could I have this one?「これを貰えないでしょうか?」を使う。
●「なぜ日本に来たのですか?」は、
Why did you come to Japan? のような日本語をそのまま英語に置き換えた表現だと
「なぜ日本に来たのですか?」のようなニュートラルな(中立的な)意味ではなく、
「あなた、日本になんで来たんですか?」のように、Why?だと否定的に聞こえてしまうので、
What brought you to Japan? を使う。

※2023/02/11「滋賀の教育の集い」で
藤原和彦さんが「Why?だと否定的に聞こえてしまうのに中学校教科書では会話文でWhy?を連発している。訂正すべきだ。」と指摘されていたのを聞いて、ナルホドと思いました。
素晴らしいご指摘です。以下のアコーディオンで、この話題を展開しています。

※2023/02/11「滋賀の教育の集い」で
藤原和彦さんが「Why?だと否定的に聞こえてしまうのに中学校教科書では会話文でWhy?を連発している。訂正すべきだ。」と指摘されていたのを聞いて、ナルホドと思いました。
素晴らしいご指摘です。
以下のように、否定的なニュアンスとそれを避ける方法があります。
●Why ~ you ~?「なぜあなたは~?」
(なんであなたは~するのか! と非難)
→ What? で無生物主語にして言い換え
●Are you going to ~?「~するつもりですか」
(するつもり? やめてくれよ!と非難)
→現在進行形「(これから)~するんだ」で言い換え
●Since when?「いつから?」
(いつから~するようになったのか!という非難)
→ふつうにHow long?にする
こういうことを伝えることが本当の話し言葉の指導だとルターは思っています。
態度(attitude)③「2文構成」「述べる順番」「段落構成」「談話文法」
文化と態度の両方を含むものとして「2文構成」「述べる順番」「段落構成」「談話文法」があります。
●「英語は2文構成を好む」(ルターの言い方では『行間が狭い』)ので、
This is a present for you. I hope you’ll like it.
「プレゼントです。気に入ってもらえるといいんだけど。」
●英語では、述べる順番は「結論が先、詳細が後」だから、
I like dogs. They are cute.
「私は犬が好きです。 かわいいし。」の順番で言うのが良く、
「かわいいので、犬が好き。」という日本語を英語にする場合に、
日本語に合わせてBecause で始めるのではなく、英語らしく「結論が先、詳細が後」で、
I like dogs because they are cute. にする(DeepL翻訳でもそうなります)。
●「段落構成」はいわゆるパラグラフライティングです。
日本語の感覚で書かれた「天声人語」のような文体とは異なります。
●「談話文法」は、日本語の「てにをは」に相応する「冠詞、形容詞(some)名詞(単数形・複数形)の使い方」、または「句と節の選び方」などをルターは想定しています。
オーラル中心の英語教育がダメな理由の決定打は④内田樹さんにお任せしましょう。
④内田樹(たつる)さんの見解「オーラル中心の語学教育は愚民をつくる」
以下の内田樹(たつる)さんのブログ「内田樹の研究室」の抜粋をお読みいただくと分かります。
オーラル中心の語学教育がいかに愚民をつくるか…。
文法と古典を取り上げていきたいですね。
★以下引用
●リンガ・フランカのすすめ 「内田樹の研究室」
植民地ではオーラル中心の語学教育を行い、読み書きには副次的な重要性しか与えない。
これは伝統的な帝国主義の言語戦略である。
理由は明らかで、うっかり子どもたちに宗主国の言語の文法規則や古典の鑑賞や、修辞法を教えてしまうと、知的資質にめぐまれた子どもたちは、いずれ植民地支配者たちがむずかしくて理解できない書物を読むようになり、彼らが読んだこともない古典の教養を披歴するようになるからである。
植民地人を便利に使役するためには宗主国の言語が理解できなくては困る。
けれども、宗主国民を知的に凌駕する人間が出てきてはもっと困る。
「文法を教えない。古典を読ませない」というのが、その要請が導く実践的結論である。
教えるのは、「会話」だけ、トピックは「現代の世俗のできごと」だけ。
それが「植民地からの収奪を最大化するための言語教育戦略」の基本である。
「会話」に限定されている限り、母語話者は好きなときに相手の話を遮って「ちちち」と指を揺らし、発音の誤りを訂正し、相手の「知的劣位」を思い知らせることができる。
「現代の世俗のできごと」にトピックを限定している限り(政治経済のような「浮世の話」や、流行の音楽や映画やスポーツやテレビ番組について語っている限り)、植民地人がどれほどトリヴィアルな知識を披歴しようと、宗主国の人間は知的威圧感を感じることがない。
しかし、どれほどたどたどしくても、自分たちが(名前を知っているだけで)読んだこともない自国の古典を原語で読み、それについてコメントできる外国人の出現にはつよい不快感を覚える。日本の語学教育が明治以来読み書き中心であったのは、「欧米にキャッチアップ」するという国家的要請があったからである。
http://blog.tatsuru.com/2010/05/12_1857.php
戦後、オーラル中心に変わったのは、「戦勝国アメリカに対して構造的に劣位にあること」が敗戦国民に求められたからである。

内田さんの最後の一行「戦後、オーラル中心に変わったのは、『戦勝国アメリカに対して構造的に劣位にあること』が敗戦国民に求められたからである。」というのはちょっと違うかな。
もちろん、カムカム英語のような話し言葉の英語を普及させることが占領下に始まったと思いますが、学校現場での訳読方式は相変わらずだったのではないでしょうか。
日本の英語教育が劣化したのは明らかに1966年生まれ(丙午で出生率が少ない)の歳からです。中学校の学習時間が週4から週3に減った。高校ではサイドリーダーとグラマーの時間がなくなった。同じ小中高を卒業した兄・姉が受けていた英語教育からすると、明らかに劣化しています。
1978年のゆとり教育の導入により1981年からは、それまでの週4時間から週3時間になった。
https://www.waseda.jp/sem-fox/memb/18s/oshima/oshima.index.html
●2004年04月27日 砂場の英語と『太陽の涙』 「内田樹の研究室」
http://blog.tatsuru.com/archives/000089.php
外国で暮らしたり、インターナショナルスクールに入れたりして、英語話者のあいだ
に置かれると、子どもは仲間や先生とすぐに「ぺらぺら」話すようになる。
それを見て「ネイティヴのような発音だ」と親は喜ぶが、これはしょせん「砂場の英
語」に過ぎない。
「砂場の英語」から「教室の英語」のあいだには乗り越えることの困難な段差がある。

以上は、2011.02.23のブログ記事 「読み書き中心で文法と古典を取り上げていきたい」に大幅加筆して再構成しました。
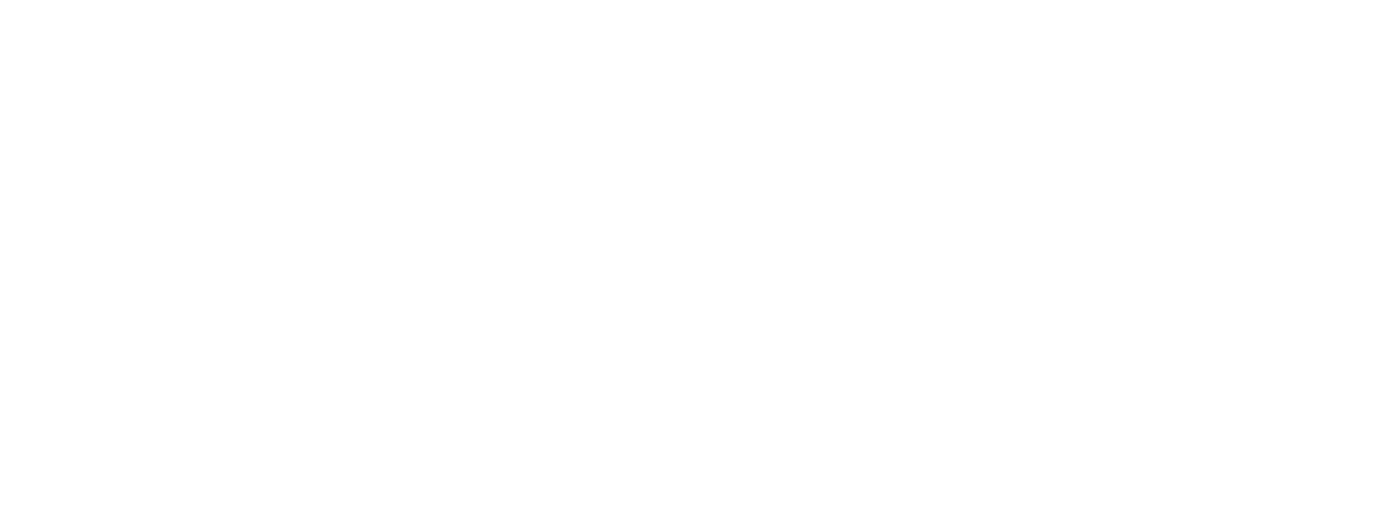


コメント